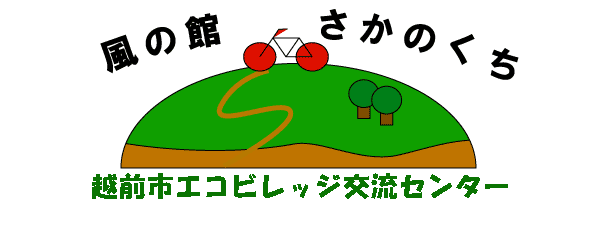
紹介
情報
新聞
「風の館」
マップ
のルーツ
合せ
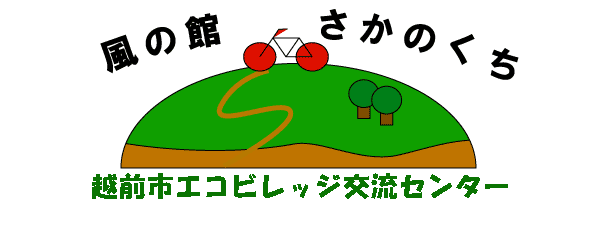 |
||||||||
| HOME | センター 紹介 |
イベント 情報 |
エコビレ 新聞 「風の館」 |
解説案内や講演依頼おすすめ自然体験 |
アクセス マップ |
坂口の魅力と見所 | 馬借街道 のルーツ |
お問 合せ |
| 馬借街道(西街道)の名称は、武生(府中)から西に向かい河野浦に至ったからで、宇治拾遺物語(平安時代の説話をまとめ、鎌倉時代に発刊)にこの街道の話が既に記載されていることから、かなり古くから人の往来があったものと思われる。 また、中国、朝鮮などのアジア大陸から海流に乗って、多くの渡来人が河野海岸から武生へ外来文化をもたらした古道が西街道であり、河野浦は越前国府の外港として利用されていた。 |
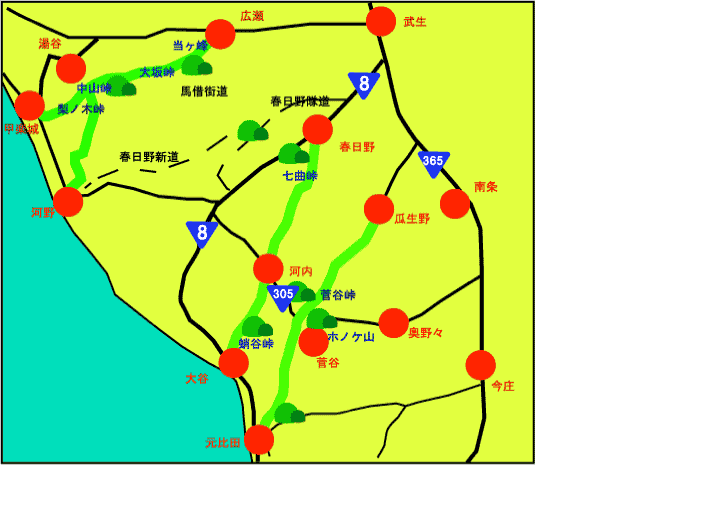
| |
|
| 敦賀-(海上七里・船)→河野(河野、今泉、甲楽城)浦-梨ノ木峠(標高260m)-中山峠(標高248m)-湯谷-大坂峠(標高280m)-当ヶ峰-広瀬-武生(府中) *江戸時代、船は長さ約7尋の伝渡船で、敦賀-河野間を1日2往復運行。 *河野浦から中山峠に行く道には、尾根の道「甲楽城坂道」と沢沿いの道「今泉道」の2通りがあった。 |
|
| |
|
| この道は木ノ芽峠(628m)のように今庄の険しい山々を越えずに済み、府中から海へ抜ける最短距離、約15kmである。(今も昔も少しでも楽に近道をしようという考えは変わらないものである) | |
| |
|
| 船で大量の物資を運べるので、河野浦が北前船で栄えた江戸時代をピークとして物資輸送路として重要な街道であった。(京都からの荷は大津から琵琶湖を船で海津まで運び、そこから愛発を越えて敦賀、そこから海上七里で河野浦、そして西街道)しかし、明治以降になると、北前船は汽船に変わって河野浦へは寄港しなくなり、また鉄道も開発され衰退していく。 | |
| |
|
| ・南北朝時代(1337年) 北朝方の斯波高経がこの道を通って甲楽城浦から出航し、金ヶ崎に立てこもる新田義貞の南朝軍を攻めている。 ・朝倉氏の土木工事(1504年、1516年、1534年) 越前守護となった朝倉氏は、南からの織田信長の侵略に備えて、道幅を九尺、側溝を設けて排水に留意し、非常時に道が泥濘になるのを防いだ。(今泉道の整備) ・羽柴秀吉の攻撃(1573年) 信長の命を受けた秀吉は、河野浦を今泉から攻め上がりこの道を通って府中に入り、柴田勝家の軍と合流して朝倉方を打ち破っている。この時、朝倉方であった西街道筋の民家や寺はことごとく焼き払われたという。 |
|
| |
|
| ・中臣宅守の配流 天平の頃(729〜48年) 延喜式 ・けいとう坊の話(甲楽城の渡しで念力を使う) 宇治拾遺物語 ・源義経一行の逃避行(この西街道を利用した可能性あり。弁慶の足跡伝説) ・親鸞上人(1207年) 蓮如上人の旅路 |
|
| | Top | | |
| Copyright (c) 越前市エコビレッジ交流センター 2001 All Rights Reserved. | |