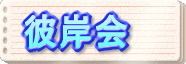 |
彼岸の入りから彼岸明けまでの一週間、先祖を供養し、お墓参りなどが行われます。
「彼岸」という言葉は、「向こうの岸に渡る」という意味のインドの言葉に由来します。
法華経の中に「彼岸」の精神について、「このように迷いや苦しみの多いこの岸(此岸)から、生まれかわり死にかわりを超越した理想の状態である向こうの岸(彼岸)、仏様のおられる安らぎのある向こうの岸に少しでも早く渡れるようになりましょう」とあります。
「春分の日・秋分の日」は、昼と夜の長さが同じで太陽は真東から昇り真西に沈んでいき、太陽がどちらかに偏ることがありません。
このどちらにも偏らないということが、とらわれを離れた正しい判断・行動をなすこと、つまり仏さまの悟りを実践する「中道」の考え方と結びついて、彼岸の「中日」を尊ぶようになりました。
|
春季彼岸(3月)
秋季彼岸(9月) |
|

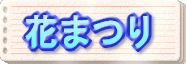 |
お釈迦様のお生誕を祝う祭りです。
白象が胎内に入る夢を見た摩耶夫人が、故郷に帰る途上のルンビニ園の沙羅の林で急に産気づきお釈迦様がお誕生になりました。
この時、甘露の香水(甘茶)が天より降ったと仏伝に伝えられています。
堂内に花御堂を飾り、その中に右手で天を指し左手で地を指している「誕生仏」を安置し、甘茶を注ぎ、無病息災・長寿、・安穏を願います。
甘茶をお配りしていますので、お持ち帰りを希望の方は、入れ物をご持参ください。
|
花まつり(4月8日) |
|

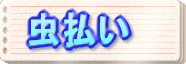 |
信行寺に伝えられてきた宝物を後世に永く伝えていくため、年に一度虫干しと保存に必要な手入れをし、参詣者に披露いたします。
|
虫払い法要(7月28日)
|
|

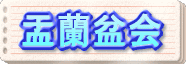 |
餓鬼の苦しみを受けている人に飲食を施し、亡き人のために供養することによって功徳をつむための法要です。
また先祖の霊と共に有縁無縁の霊、法界万霊に供養を献げ、全ての生きとし生けるものに感謝する法要でもあります。
当日は、檀信徒の方々や親戚の方々が多数お参りされます
|
盂蘭盆施餓鬼会法要(8月第1日曜日)
|
|

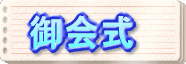 |
日蓮聖人は弘安5年(1282)10月13日に東京池上の地でご入滅されました。
この日を中心にして全国各地の日蓮宗寺院で報恩会の法要が営まれます。
信行寺では、毎年「文化の日」に営まれます。
|
御会式法要(11月3日) |
|

|